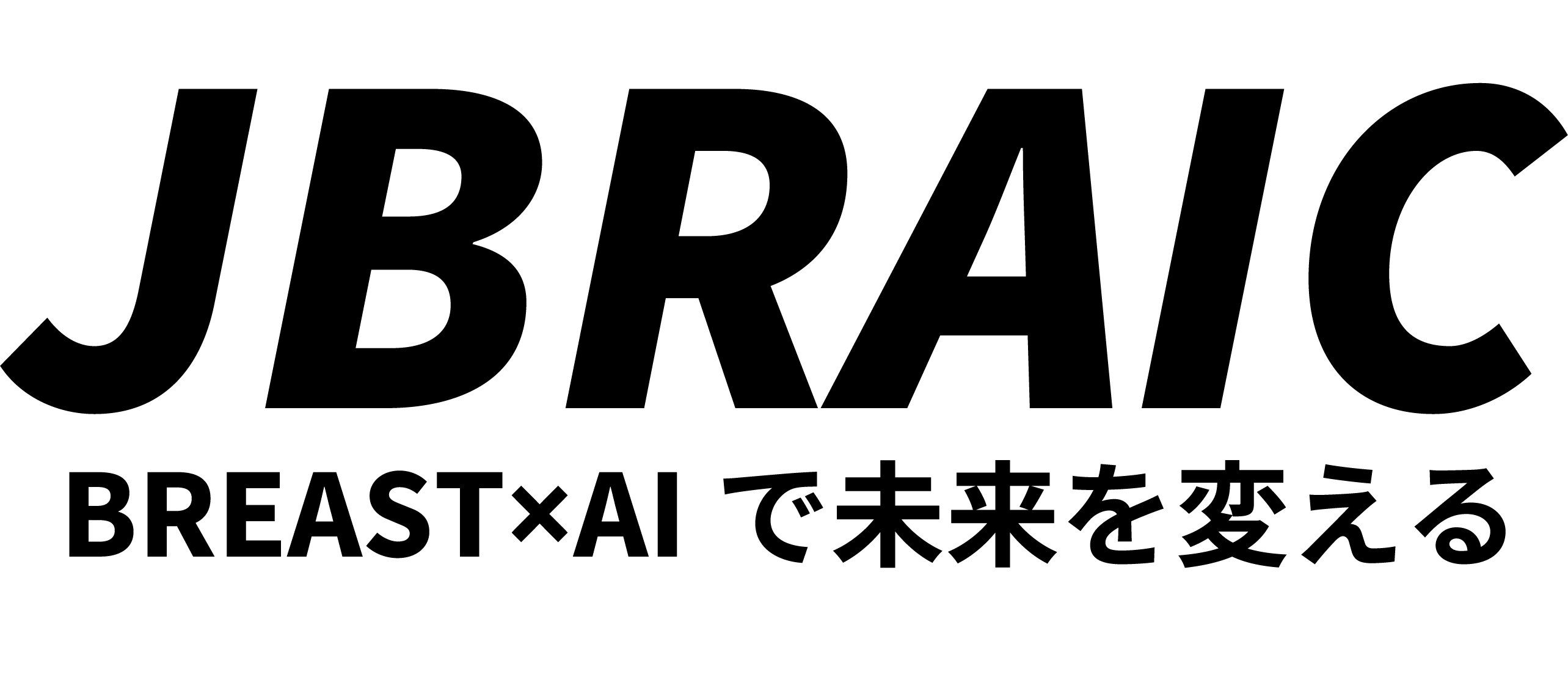
PICK UP
|双方向型|
専門医が答える、あなたの疑問

本年度、日本乳腺人工知能研究会では、群馬県内の患者様より実際に寄せられた切実な疑問・質問に対し、乳腺専門医が直接回答する形式でのQ&Aセッションを実施いたしました。
医療技術やAI(人工知能)の進歩は目覚ましいものがありますが、治療に向き合う患者様が抱える「迷い」や「不安」を解消するのは、やはり信頼できる正しい情報と、人の言葉による丁寧な説明です。本セッションでは、診察室では聞きそびれてしまいがちな具体的な悩みについて、医学的根拠に基づきつつ、患者様の心情に寄り添った回答を心がけました。
本セッションの内容は、内容を一般化し、公開しております。
治療の選択に迷われた時、ふと立ち止まった時に、このQ&Aが皆様の道標となれば幸いです。
第4回 日本乳腺人工知能研究会 総会 開催案内(更新)
テーマ:『 医療AI × 人の創造 〜調和そして創出へ〜 』
| 会期 | 2025年5月17日(土)13:00~17:20 |
| 現地現地会場 | 墨田区産業共創施設 SUMIDA INNOVATION CORE『THE STAR』 |
| 開催形式 | 現地開催とWEB開始の併用開催(ハイブリッド形式) |
| 当番世話人 | 椎野 翔(新松戸中央総合病院) |
| 代表世話人 | 国際医療福祉大学成田病院乳腺外科学 黒住 献 |
| 特別講演 | 堀口 淳 先生(国際医療福祉大学医学部乳腺外科学 教授[代表]) |
| 特別講演 | 下井 辰徳 先生(国立がん研究センター中央病院 腫瘍内科) |
| 顧問 | 亀田総合病院 乳腺科 乳腺病理部長 黒住 昌史 |
| 顧問 | 日本乳腺人工知能研究会顧問 国際医療福祉大学医学部乳腺外科学教授[代表] 堀口 淳 |
| 顧問 | 乳がん検診精度管理中央機構理事長 国立病院機構渋川医療センター特命診療顧問 横江 隆夫 |
本研究会は、乳腺疾患領域における人工知能技術の発展と臨床応用の促進を目指し、活発な意見交換の場となることを目的としております。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
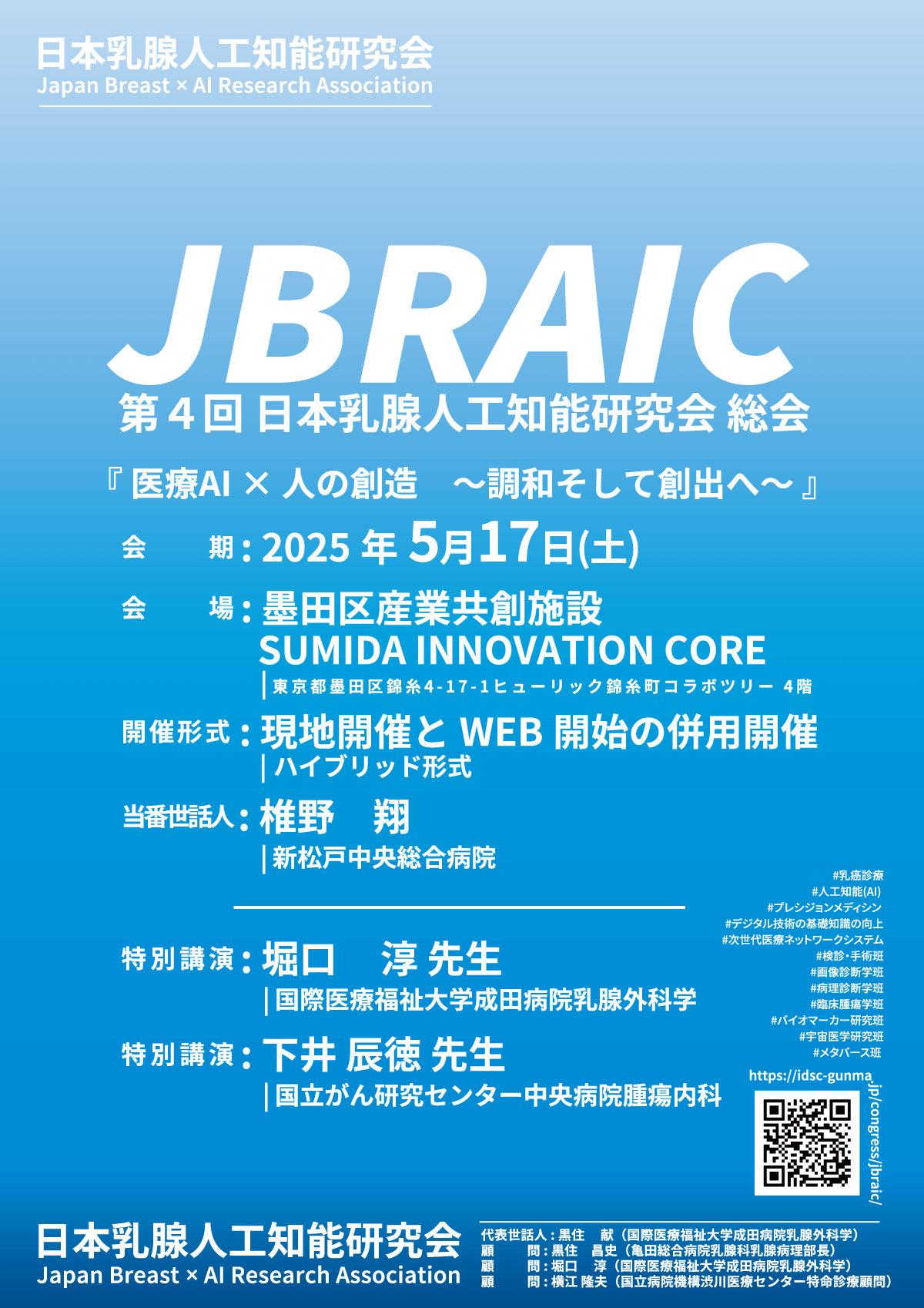
|双方向型|市民公開講座
医師に聞きたいこと、あなたの言葉で。

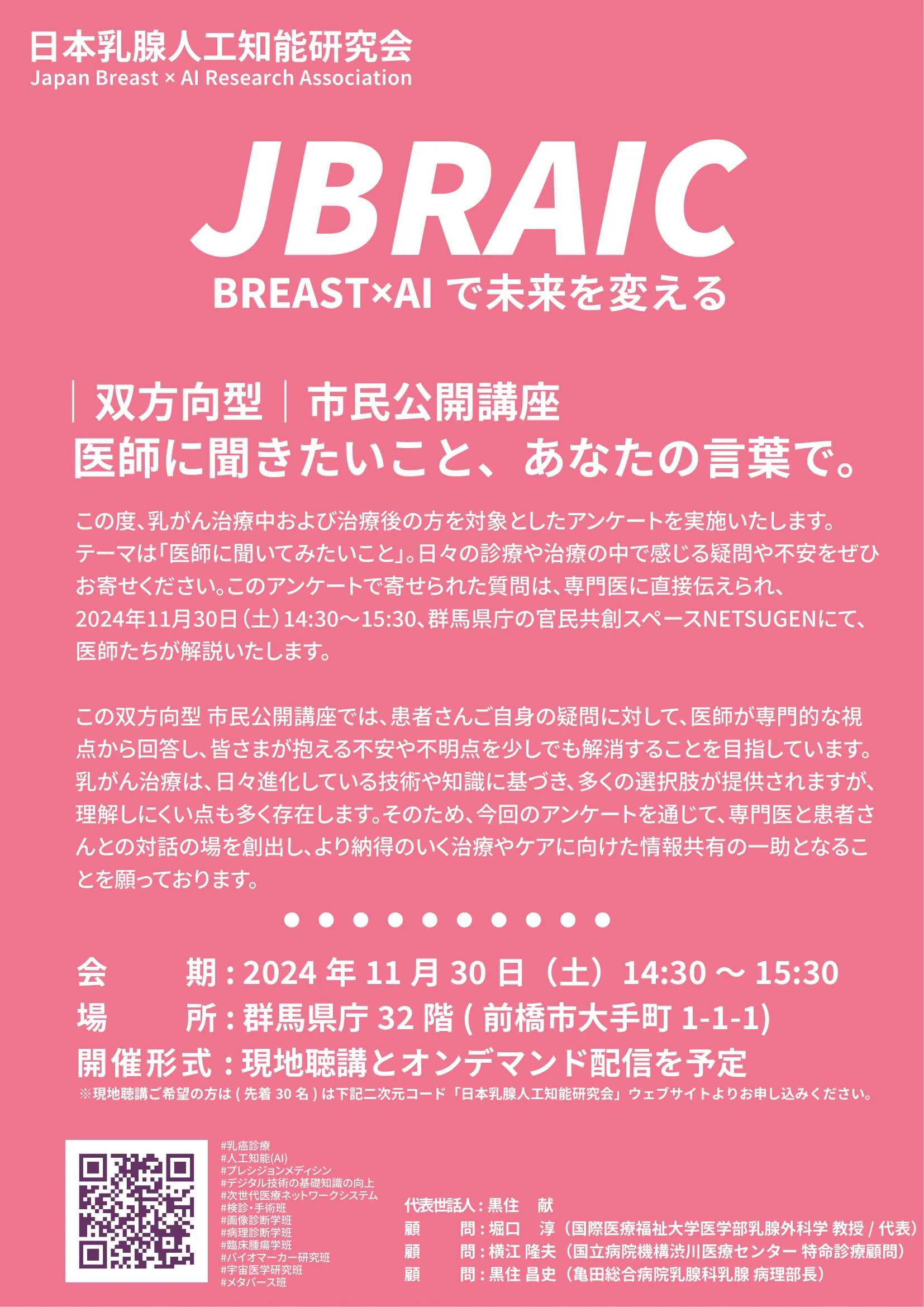
2024年11月30日(土)、群馬県庁32階にて乳がん治療に関する市民公開講座「医師に聞いてみたいこと、あなたの言葉で」が開催されました。
本講座講座では、事前に集めた質問をもとに、治療に関する疑問に専門医が直接お答えしました。オンデマンド配信も行っていますので、ご自身のペースでご覧いただき、少しでも治療への理解が深まればと思います。
がん治療に取り組む際、不安や戸惑いはつきものです。普段は冷静に判断できることも、治療に直面すると揺らぐことがあります。だからこそ、正しい情報を得ることが大切です。今回の講座が少しでも皆さんの不安を解消し、正しい情報を得る手助けになれば嬉しく思います。
日本乳腺人工知能研究会は、これからも、デジタル技術と人間的なケアを融合させ、より多くの患者さんに寄り添った情報を提供していけるよう努めてまいります。
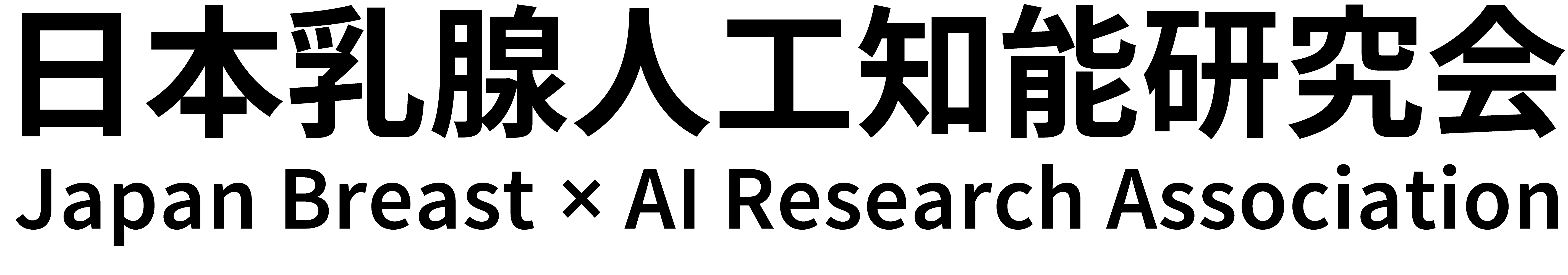
代表世話人ごあいさつ
日本乳腺人工知能研究会の代表世話人に就任致しました黒住献と申します。
昨今、人工知能を用いた医学的研究は急速なスピードで発展を遂げており、中でも深層学習を用いた画像診断および病理診断技術の向上は著しいものがあります。それ以外の医学研究分野においても、人工知能などのデジタル技術を応用した新たな医学研究が多く進められてきています。そこで今回、人工知能などの革新的デジタル技術を用いた乳がんの診断・治療に関する臨床研究および基礎研究を行う研究会を立ち上げることに致しました。この研究会は運営、学術集会などをすべてオンラインで行う新しいタイプの研究会です。
医療現場における乳がんの診断・治療には、乳がんにおける分子生物学的特徴を理解することはもちろんのこと、選択された手法に関して、そのリスクやベネフィットを含めた臨床腫瘍学に関しての豊富な知識と経験が必要とされます。しかし、現実の問題としてそれを的確に行うことができる医師は世界各国で未だ不足している状況です。特に地域医療の現場や発展途上国における専門医不足は深刻な問題であります。本研究会では、人工知能などのデジタル技術を用いた革新的医療技術の臨床的信頼性を検証し、医療現場への導入のためのネットワーク構築を目指します。このことは偏在化した地域医療や発展途上国における医療の均一化につながると考えております。
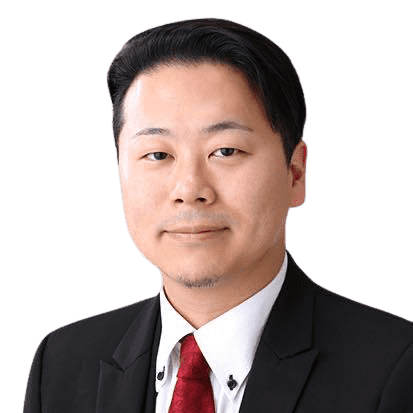
また、近年の乳がんにおける診断・治療技術の発展は乳がん患者さんの予後を大きく改善しました。しかしながら、いまだに予後の悪いタイプの乳がんが、一定数で存在するのも事実です。そのため、少しでも多くの人々が安心した人生を送れるように、医療従事者、医学者の方々は、診療、研究、教育に懸命に従事しております。デジタル医療技術を用いることにより、日々多様化していく乳がん診療の中で、医療従事者と患者さんが共に無理のない形で乳がん診療を進めていける環境を創造するために、微力ではありますが本研究会員の皆様とともに、ぜひとも新しい時代の医療および医学の現場に対応できる研究会にしていきたいと思っております。
国際医療福祉大学医学部乳腺外科学
黒住 献
日本乳腺人工知能研究会_理念
#1.
人工知能(AI)技術を中心とした革新的なデジタル技術を基盤として、乳がん診療におけるビッグデータ(疫学情報・医療画像データ・臨床病理学的情報・網羅的遺伝子発現解析データ等)から新たな知見を見出しかつ臨床応用することによって、患者個人レベルでの最適な治療法選択(プレシジョンメディシン)の実現を目指す。
#2.
高度なデジタル技術を応用することによって、専門的な乳がん診断・治療技術が可能な次世代医療ネットワークシステムの構築を可能とし、かつその臨床的有用性を証明することで医療現場への導入を目指す。
具体的には、遠隔地などの偏在化した地域医療や発展途上国における医療の均一化を進め、さらに将来的には宇宙医学研究への応用を図る。
#3.
各職種者(バイオインフォマティシャン・病理医・医学研究者・基礎研究者・法律専門家等)の多分野にわたる高度な知識を統合し共有することによって、研究会参加者全体の革新的デジタル技術に関する基礎知識および技術力の底上げを推進し、かつ参加者全体の幅広い研究活動の展開を目指す。
